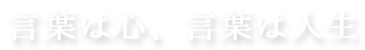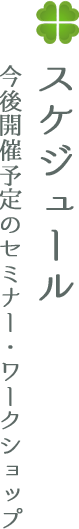「マリンブルーな季節 2019」 9

9
「あまり女の人と、食事をしたことがないもんで」
店を探して歩きながら、山内は恥ずかしそうに頭を掻いた。
あのライブの翌日も、真奈子はライブハウスに行った。ライブの終わる時間を見計らって、楽屋口で待っていた。そして自分の方から山内に声をかけた。これまでの真奈子からは想像もできない行動だった。
「あなたみたいに若い女の子を連れて行くような店、トレンディーって言うんですか、そういうの全く知らないんですよ。あ、トレンディーも、古いか」
「どこだって、いいんですよ」
「どこでもいいったってねえ。この時間だし。まさか、ガード下の焼き鳥屋に連れて行くわけにもいかないし」
「え、ガード下? 行きたい、行きたい。そこ連れて行ってください」
「ダメ、ダメ。だいたいあなた未成年でしょ。お酒飲めないでしょ」
「お酒を飲まなければ、いいでしょ。ウーロン茶でも飲みますから、ご心配なく」
「もう、あんまり苛めないで下さいよ」
言いながら、ハァと大きく息を吐いた姿がおかしくて、真奈子は大声を上げて笑った。
「もう、あなた、あなたって、わたし真奈子って名前なんですよ」
「それは失礼。それでは、改めまして、真奈子さん」
名前で呼ばれて、真奈子は頬が火照るのを感じた。
「仕方ない。それではとっておきの店にでも、お連れしますか、お嬢さん」
真奈子は、また笑った。おかしくてたまらなかった。嬉しくてたまらなかった。真奈子にとって東京へ出てきて、いや、人生で初めて、心の底から笑った夜だった。
「こんなに早く電話が掛かってくるとは、思っていませんでしたよ。それにしても、今どき東京タワーなんて、珍しいことを考えるお嬢さんだ」
ガード下の焼き鳥に連れていってもらった夜、今度はいつかと食い下がって、また会ってもらった。
けれど、その先のことは約束できないと言われ、それならと、ラインはやっていないと渋る山内からスマホの電話番号を聞き出したのだった。
山内は、バンドのマネージャーらしく音楽の知識が豊富なのはもちろんのこと、本にも詳しく、「こんな本は、どうか」「あんな本も、また面白い」と、色々なことを教えてくれた。
真奈子は、山内と話を合わせたくて、勧められた本を次から次へと読んだ。
東京タワーで待ち合わせたいと言い出したのは、真奈子の方だった。
「1度、来てみたいなって、ずっと思ってたんです」
「しかし、他にいくらでも若い人の行くところはあるでしょう。東池袋のサンシャイン60とか恵比寿のガーデンプレイスとか。いや、もうそれも古いか。今ならやっぱり六本木ヒルズかな。ああ、それも、もう古いか。えーっと、あ、そうそう、スカイツリー! って、これも、できて何年も経ちますねぇ」
「いいの、いいんです。東京タワーがいいんですってば」
「いや、まいったな。そうですか。あなたたちの世代だと、逆に東京タワーの方が、新鮮なのかな。レトロ感覚っていうか。あれ、もしかして僕に合わせてくれたのかな」
「山内さんは、東京タワーには何度も来たことあるんですか」
「僕は見ての通りのおじさんだし、それに僕が東京に出てきたときからあるのは、この東京タワーだけですからね」
「へえ ― 。失恋した時に、1人で泣きに来たとか」
「はは、失恋ねえ……失恋かあ。それより、どうしてこの世には、男と女がいるんでしょうねぇ」
予期せぬセリフに、真奈子は思わず山内の顔を見た。
「いや、失礼。あなたのような未来のある若者に言うことではありませんでしたね。昔はね、人恋しくなると来たもんですよ。このネオンの下にたくさんの人がいると思うだけで、なんだか嬉しくてね」
2人のいる特別展望台は、地上250mにある。
日はすっかり落ちて、すでに辺りは広大な光の海と化していた。
「かなわない」
真奈子は思った。
「とっても、かなわない」
自分の育った鳥羽の田舎町の空気は、ほんのちょっとした出来事にも大きく揺れるだろう。ところが、この街ときたらどうだ。何もかも飲み込んでしまって平然としている。
圧倒的な数と広さ。
力任せの迫力の前に、真奈子は言葉を失った。なんという所へ、自分は来てしまったのか。夢を握り締めていたはずの掌を開いてみたら、そこには何もなかった……まるで蜃気楼。
今ごろ、みんなどうしているだろう。
短い夏休みの間に再会した田舎の人々の顔が、広大な光の海の中に、次から次へと浮かんできた。重いと感じていたはずなのに。友だちなんかいないと思っていたはずなのに。どうして、こんなに沢山の人たちの顔が浮かんできてしまうのだろう。
「まさか、ここから飛び降りようってんじゃないでしょうね」
おどけた調子の山内の言葉に、我に帰る。
「飛び降りようと思っても、これじゃあね」
はめ込み式のガラス窓を、軽く叩いて見せる。
「さてと。今日はとっておきの店に連れて行きましょうかね」
「この前も、確かそう言いましたよ」
「それで、行った店が……」
「おでん屋さん!」
真奈子が元気良く、声を上げた。
隣で囁き合っていたカップルが何事かと2人を見たが、またすぐに顔を寄せて囁き始めた。
「さ、行きましょう。もう僕らのいる時間帯じゃない。カップルの邪魔をしちゃあ、悪いですよ」
別にいたって、いいじゃない。わたしたちだって、傍から見れば立派なカップルだわ。
真奈子は思った。
が、今日はどんなとっておきの店へ連れて行ってくれるのか。どんな話を聞けるのか。そちらの方への好奇心も捨てがたく、おとなしく山内の言葉に従った。
「へえ、山内ちゃんが女連れなんて、珍しいじゃない」
新橋の路地を入ったところにある小さな居酒屋に入ると、店のおやじさんが開口一番、こう言った。
「あなたは ……、真奈子さんはウーロン茶ですね」
真奈子の返事も待たずに、勝手にウーロン茶を注文する。
「どうぞ、ごゆっくり」
ビールと口取り、それにウーロン茶をテーブルに置きしな、おやじさんが肘で山内を軽くこずいた。
「山内ちゃん、いいの。こんな若い女の子を連れ回したりして。犯罪だよ、犯罪」
「うるさいな、ほっといてよ。親戚の子だよ、田舎の親戚の子」
やっぱり、私は田舎ものか。つい、俯きがちになる。
「ごめん、気にした?」
山内が申し訳なさそうに聞いた。
「いいえ、別に」
言いながら、真奈子はすでに笑っていた。
「ロックバンドのステージがある店はね、まず渋谷ね。渋谷、知ってるよな」
酔いが回ってきたのか、山内の口調が親しげになってきた。真奈子は嬉しくなる。
「あと、新宿だろ。それから、忘れちゃいけない、目黒の鹿鳴館。ここはロッカーの目標、夢の舞台なんだ! 出来てから30年は経つ老舗のライブハウスでさ。30年前って、生まれてた? ない? そうだよな、んなわけないよな。俺は生まれてたよ、すっかり生まれてた。聞くな、その時いくつだったかなんて、いいか、聞くな。これで結構、気にしてんだぞ、歳を」
酔った山内は面白かった。普段とのギャップが大きいだけに、余計面白かった。
「ここの舞台に立つのは、そりゃあ大変なんだ。テープ審査だろ、ライブ審査だろ。もう厳しくって、厳しくって、泣いちゃうぞ。俺、泣いちゃうぞ、いいか。でもさ、業界の新人スカウトの担当とかも見に来てさ。目にとまれば、メジャーデビューもぐっと近づくってな。そうなったら、俺泣いちゃうよ。嬉しくってさ、俺またまた泣いちゃうよ」
とうとう、真奈子は吹き出した。
困ったとき、迷ったとき、そして寂しいとき、真奈子は長内に電話をかけた。
たまにスイッチの切られていることもあったが、ほとんどの場合、山内は優しく気長に真奈子の話に付き合ってくれた。
いつでも、どこでも、どんな時でもスマホを通して自分は山内と繋がっているのだという安心感。真奈子は山内の存在を通して、自分が今ここにいるのだと、実感できた。山内という鏡になら、自分の姿を映して見ることができると知った。
♪※。.:*:・’°☆♪※。.:*:・’°☆
昨年から手掛けていた本が、ようやく出版されました。